「人の反応や外側のことが気になり、あれこれ考えては疲れてしまう」というA子さん。
私たちが「あれこれ考えてしまう」とき、「外側の状況に悩まされている」というよりは、「自分の空想に悩まされている」ということが起きています。
「これはひどいことだ」とか、「大変なことになる」とか、その状況に対して自分なりの意味づけや価値判断を下しており、その結果「きっとこんなことが起こるに違いない」と考えることで疲れてしまうのです。
しかし、それらは空想なのです。事実とは関係ありません。
それならば、まず空想をストップするためにアタマのおしゃべりを鎮めてみましょう。
出来事に対する、意味や意見、判断、解釈、ストーリーを停止してみます。
この空想さえなければ、ものごとの意味や解釈、価値判断もやんでくるのです。
ものごとはまっさらな状態になります。

私たちが動揺しているとき、「その出来事や状況そのものに混乱させられている」と感じがちですが、動揺の原因は「自分の考え」であり、空想にホンロウされている、ということなのです。
私たちは状況を目にしたとき、瞬時にそれが自分にとってどういう意味があるのか、ストーリーを決めつけてしまいます。
あまりに瞬時のことなので、自分で決めつけをしていることにさえ気づきません。
そして、それを何の疑いもなく信じこんでしまいます。
それらはたんに、「自分の勝手な空想だ」「でっちあげだ」ということがわかりません。
それは実際、事実とは違うイメージや予測であり、決してほんとうのことではないのです。
真実ではないことを信じることによって、自分で自分を苦しめてしまいます。

ものごとにはもともと、「意味」というものはついてはいません。「ただ、そのように起こっている」だけなのです。
「意味」とは誰かによって与えられるものであり、ものごとを解釈するモノサシとなります。
そのモノサシが悲惨であれば、ものごとは悲惨なものとなり、モノサシが楽観的であれば、楽観的なものとなるのです。
つまり、自分で自分を怯えさせることもできれば、自分を希望で満たすこともできるのです。
どちらを選ぶこともでき、自分のこころが取り入れた考えを私たちは目にすることになります。
それが、私たちのこころのパワーです。
それならば、見たいものだけを自分の判断として選ぶことです。

自分で自分を混乱させたり、怯えさせないための解決策は・・・つねに「こころを安らかに保っておくこと」です。
といっても、考えは良いものも悪いものも次から次へと勝手に浮かんでくることでしょう。
ただ、勝手に湧いてきては消えゆくものに対して、積極的に関わることはやめましょう。
考えが現れたことに気づいたら、即座に反応することはせず、ただほっておきます。それらを通りすぎさせてあげるのです。
「それは問題だ!」と大騒ぎしないかぎり、それは問題とはなりえないのです。
湧いてきた考えに反応せず、さらなる思考に巻きこまれることがなければ、それらはただ静かに消えて行きます。
あることをずっと考えつづけることの方が努力のいる作業であり、相当なエネルギーを消費するものなのです。
どうしても自分の思考が気になってしまうのなら、ラジオやテレビのボリュームを下げるように、イメージで思考の音量ツマミを回すか、あるいはリモコンのボタンを下げるなど、実際にその動作をしてみましょう。
自分がその「音」を調整していることを思い描くことで、実際に思考の音量を下げる感覚が得られます。

目のまえのものごとに対して、自分自身が川縁に立って、静かに流れを眺めているようなイメージをしてみるのもいいでしょう。
目の前の流れにただ身を任せるように、ものごとを受け入れ、過剰に反応しないこと。これによって、あなたのこころは次第に静けさを取り戻します。
自分が見ている画面から数歩後ろにさがるようなイメージをしてみます。古い映像を眺めているように、少し俯瞰して見るのです。
自分が出来事に積極的に関与し、右往左往するのではなく、ものごとが自然と流れゆき、いちばんよい落としどころにおさまってゆことをイメージし、信頼してみましょう。
それは、誰にとってもベストな落としどころなのです。
そして、こころに静けさをとりもどすことで、この静けさがものごとすべてに反映されます。そして、それらを正しく解決してくれることを信頼してみましょう。くつろいで成り行きにまかせるだけでよいのです。
かならずや、「これがいちばんよかった」という納得の結果を目にすることができるはずです。
(「気づきの日記」バックナンバーはこちら: 古川 貴子/ ヒプノセラピー・カウンセリング )

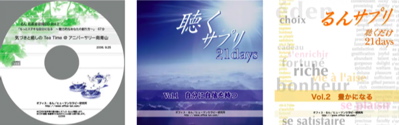
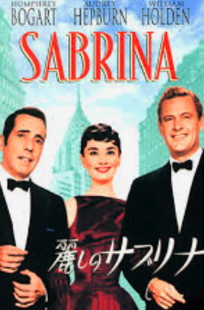
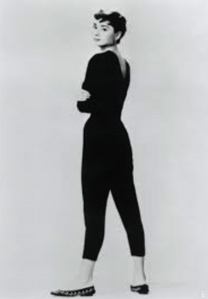




 セラピーCDなど販売中
セラピーCDなど販売中